「経営の勉強をしなければと思いながら、経営の勉強ができていないあなたへ」
いつか「経営をしっかり勉強しなければ」と思いながらも、いざ経営の勉強に取り組むとなるとぶつかる壁があります。それは、経営の勉強をしたいけれど「何から手をつければいいんだろうか?」という迷いや不安の壁です。
これまで、業務で必要な知識・仕事のスキルは勉強をしてきた。
しかし、経営を上手にやるための勉強はしたことがない。
経営の勉強として、これをやれば大丈夫ということも聞いたことがない。
だから、手探りで自分なりに経営の勉強をはじめる経営者がほとんどです。
まず考えるのは、自分に必要な、自分がやるべき経営の勉強とは何か?
事業計画づくりか?戦略づくりか?営業強化か?財務ノウハウか?最新マーケティング知識か?組織づくりなのか?
経営をするために勉強しなければいけない項目を挙げてみると、あまりに多何について、どう学ぶべきべきなのか?優先順位は何からか? わからなくります。
私たちは創業以来(2023年創業27周年)取り組んだ自社の多様なビジネスモルにおける経営経験と、約33,000社以上の経営支援・研修実施から、あらゆる
経営者またはこれから経営に携わる後継者や起業家が「経営の基本として勉するべき」重要ポイントを、体系的・総合的にまとめ講座の構築をしました。
それがプレジデントカデミー「経営の12分野」です。
本レポートでは、これから経営の勉強をスタートする、経営者または後継者起業予定者に向けて、より良い「経営の勉強」方法について、できるだけシプルにまとめてみました。自分なりの勉強法に不安を持つ方。経営の効率的効果的な勉強方法を探している方。限りある時間を無駄にしないために、ま何より自社の未来のために、下記に記載する「経営の勉強」を参考にしていだければ幸いです。
1 経営を勉強する方法
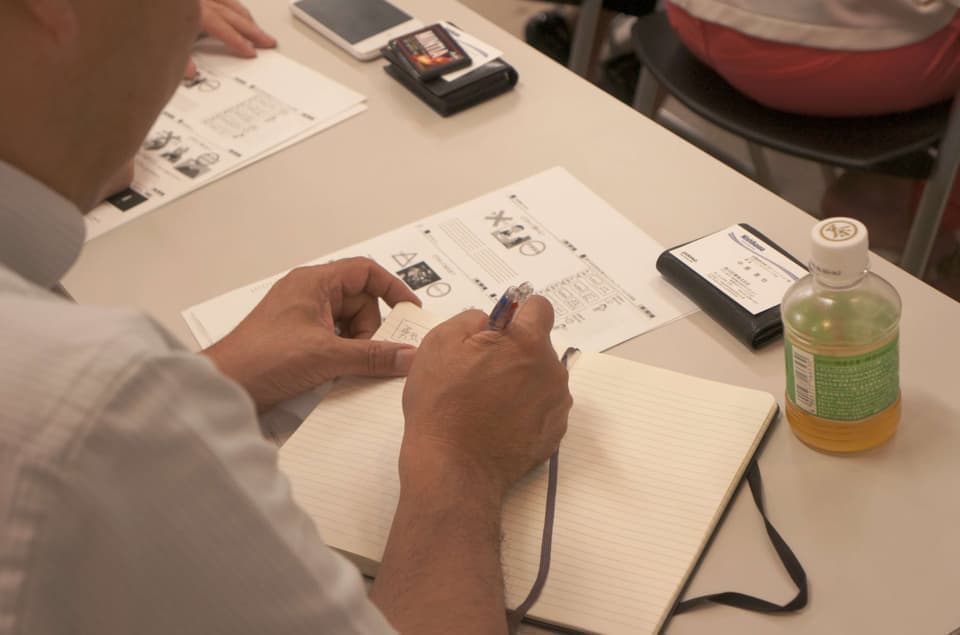
経営者はどんな方法で勉強しているのでしょうか? まず、多くの経営者がはじめて取り組む際の勉強方法をご紹介します。
<書籍・雑誌から学ぶ>
経営を勉強する初歩的な方法が「本」から学ぶというものです。成功している経営の伝記や長年の経営研究の結果などを、本から勉強することができます。たった2,000ほどで、その著者が経験した数十年という経営事象を疑似体験することができます。
だからコスト対効果が最も高いように思えるので、まず経営の勉強で取り組むべきは、「本」からだという方が多くおられます。
ただ、経営者が手にする本のジャンルは自社の業界に関係しそうなジャンル、自社が抱える課題に関係するジャンル、自分の仕事に役立ちそうなジャンルに偏る傾向あります。日頃自分から積極的に触れないことは学べないことになります。
経営雑誌の定期購読は広く社会・経済の最新情報を網羅的に収集できるメリットがあります。
しかし、雑誌は断片的で商業的な広告記事も多く掲載されています。
書籍では好き嫌いをせずに多様なジャンルと向き合うこと、雑誌については情報収集の一部と考え割り切って勉強することをオススメします。
<セミナーや研修で学ぶ>
経営を勉強する際、セミナーでの勉強も良い方法です。セミナーは、ある経営テーマに関してわかりやすく60分~120分(1日または複数日の経営者研修もあります)ほどでまとめてくれています。セミナーでは受講者が習得しやすいようスライドなどの資料にまとめてくれています。そのため、理解しやすく時間効率のいい勉強方法です。
経営セミナーは主に4つのジャンルに分かれています。
①「個人のマインドを整える」経営セミナー
②「事業構築・戦略の立て方を学ぶ」経営セミナー
③「ビジネススキルを高める」経営セミナー
④「組織や人材育成を進める」経営セミナー
費用もそれなりにかかるケースがほとんどなので、手当たり次第というよりも、自社の課題に合わせて、経営セミナーを活用していくのが良いでしょう。
地域の商工会など団体が商工振興として主催するケース、プロとして経営研修を展開する会社が主催する、ケース、ソフトウェア企業が自社製品の販売促進の目的で主催するケースなど主催者がどの立ち位置で開催をしているセミナーであるかも見定めることが大切です。
<ネット情報から学ぶ>
分からないことがあれば検索すれば大抵のことは分かる世の中になってきています。
ネット検索は、無料ですぐに経営の情報を得られるが点で優れています。昔は有料で
ないと手に入らなかった内容も、今では無料で手に入る場合もあります。
ただ、ネット検索のデメリットは情報の信用性です。フェイクニュースも多く紛れています。信用性が低い情報や嘘の情報・商業目的に加工された情報などもあります。
<経営者団体で学ぶ>
JC(青年会議所)、ライオンズクラブ、商工会議所等の経営者団体での勉強も1つ方法です。これらの団体では、職場や製造現場の視察、メンバー間での勉強会などが用意されています。一番のメリットは、地域の「経営者同士で関係をつくり」ながら勉強ができることです。地域独自の商習慣や関係性などを重視した活動となります。
勉強できる内容は先輩や同じ仲間の経営経験によるものです。
学んだ内容をどう自社に落とし込むか、先輩や同僚に相談ができる良さもあります。
<YouTubeやSNSで学ぶ>
スマホ時代に取り組みやすい、経営を勉強する1つの方法が「YouTube」やSNSから学ぶという方法です。YouTubeで勉強するメリットは、①情報の鮮度が高い②動画の視聴は学びやすい③お金があまりかからないものが多い、という点があります。
動画は移動時間なやスキマ時間を活用して勉強ができます。
しかし、YouTubeの動画は視聴者数を増やすという目的からビジネスマンをメインターゲットとしているため、ビジネススキルや自己成長に関する勉強が多くなります。
つまり、経営者が学ぶべき「経営の一部分のみ」がフォーカスされています。
また商業的な加工も多いため、活かせる情報を正しく選別できる力が必要となります。
経営を勉強する方法「選択肢」はわかった。
しかし、忙しい業務の毎日です。経営の勉強をやらなければと思いながら、忙しさで色々な経営の勉強方法に取り組みはしたものの、挫折したという方も多いはずです。
では、なぜ忙しく大変な状況でも経営の勉強をする必要があるのでしょうか?
2 なぜ経営の勉強が大切か?

漠然と「経営の勉強をしなければ」と焦る皆さんに、まず最初に私たちがお伝えしたいことは「なぜ経営の勉強が大切か?」ということです。
経営者=社長または経営に関わる者の仕事は「会社を継続させる」ことです。
そのためにありとあらゆる経営に必要な知識やノウハウ、行動が必要です。
そして、これさえすれば、誰でも必ず経営が上手くいくという魔法はありません。
各社が置かれた環境や状況に応じて、習得したあらゆる経営の知識・ノウハウを持って、経営者は自社の「見直し」と「修正」行動をし続けることが経営を成功に近づける唯一の道だと言えます。
「ズバリこれだけやればOK」という正解がない、経営という活動において「仮説を立て検証をする力」がとても重要です。この仮説を立てることに、経営の勉強が関わってきます。
経営者が、正解に近い仮説をスピーディーに立てることができたならば、投入するお金やエネルギー・時間は効率的に働きます。
つまり会社として早く成功に近づいて行くことができます。
また社員が増えると事業活動のスピードや規模の拡大は、大きなレバレッジを得て、会社は急成長します。しかし、社員が増えて、事業に課題やマイナスが解消されないまま、その解決に必要な経営者の仮説が貧弱だと、会社の経営に大きな危機をもたらすことになります。
つまり事業が順調に伸びて継続できるかどうかは、経営者が立てる仮説が良いもので、実行できるかどうか、経営者の仮説力が重要だということです。
かつてのカリスマ経営者たちは自らの「センスと度胸」=「独自の仮説力」で勝負してきました。
しかし、現代のビジネスは昔よりも考えるべきことが複雑になり、スピードも要求されます。
そのため、仮説を検討するための要素は複雑に絡みあい自分のセンスや度胸だけでは、正しく対応できない状況になっています。自分なりの仮説よりも経営を実践するために外せない基本要素を取り入れて、正しい仮説立てができるかが重要です。
これからの経営において持って生まれたセンスと度胸(自己流の経営)も大切ですが経営を継続するために「必要な仮説力をつくる」 ①経験 と ②勉強 2つが有効と言えます。
仮説力を強化していく1つ目の方法は【経験値】を高めることです。
経営者として、経験する全ての経営事象が仮説力を高めていきます。多くの場合、経験を積めば積むほど、経験したビジネスの中での仮説力は向上していきます。
経験値が高ければ、リーマンショックなどの金融危機のような急激な外部環境の変化があっても、「次は、こうしていくべきだ」という仮説を立案できるものです。
長年経営をしている方にはこの経験値が蓄えられています。
仮説力を高めていく2つ目の方法は【経営知識】です。この経営知識は、経験値と共に仮説力を高めるために大切な要素です。
経営の基本知識を知らないと、経営における正しい仮説を立てることが出来ません。
特に、経営者歴が浅く、まだまだ経験が浅い場合には経営知識が重要であり経営判断の拠り所となります。経営を勉強することは、経験値の低さを補完してくれます。
もちろん、色々な経験をしようと考え、失敗と成功を繰り返し経験値を徐々に高めようという方法もあります。
しかし、そんな悠長なことをしている経営資源と時間は、ほとんどの中小企業には無いはずです。
ですから、経営経験の浅い経営者は、なるべく早い段階で経営の勉強にしっかりと取り組み、仮説の質を底上げすることが必要です。
経験値を高めることには時間がかかります。
しかし、経営を勉強して経営知識を増やすことは短時間で行うことが出来ます。
社員に向かって経営者が「経験するまで仮説は立てられないので、待っていてくれ!」等の発言はできません。
経験値を補うために時間をお金で買う必要があるというのが、経営を勉強するもう一つの大切となるポイントです。
また、経験のある経営者が事業環境の大きな変化や時代の変化により、これまで自分が経営の経験として積み上げてきた「仮説力」が通用しなくなる場合も多くあります。
この場合には、これまでの経営経験を大切にしながらも、未来に向けて新しい経営のやり方を勉強し直して、仮説力をブラッシュアップさせることも必要になります。
このように、経営を上手く遂行するための「必要な仮説力」を強化するために、経営者に「経営の勉強」が欠かせません。
詳細は「経営を勉強する重要性」の無料レポートで説明していますので、こちらも御覧ください。
3 まず最初に社長がすべき経営の勉強とは?

経営を勉強すると言っても、経営をするために必要な事柄は多岐にわたります。
何からどれを優先して勉強したら良いのか?やはり迷い・悩む方が多いです。
またインターネットなどで情報を手軽に入手できる現代は「こうしたら儲かる」
「これで経営が上手くいく」という情報が、次から次へと目の前に現れます。
業務システムや物品を買わせるために加工された情報もあります。
あれをやらなければ、これも取り入れなければ、これに遅れてはいけないと、経営者は仕入れた情報を元に目新しい経営の取り組みをスタートさせます。
これは新鮮で良いことのように思えます。しかし、急に社長がはじめる目新しい施策に、いつも社員は疲れ、お客様は離れ、経営のやり方がブレて経営者自身も迷い悩むケースが多く見受けられます。
頑張って色々と情報を仕入れて、経営に取り組んでいるはずなのに、皮肉なものです。
そうならないために、私たちがまず最初にオススメしているのは
「経営の基本を理解(経営を体系的・総合的に把握する)して経営を実践できる」ようにしましょうというものです。
経営の基本を勉強して、経営における全体像を理解した上で、経営に必要な仮説づくりや判断をしたならばブレたり迷うことが少なくなります。
経営において「木を見て森を見ず」の状態になることも防ぐことができます。
経営の基本をおさえないまま、新しい施策に次々と取り組むだけの会社は、ムダが多いため総じて業績が振るわず、人材の退職課題も抱えていることが多いように見受けられます。
もしかしたら、こうした課題は経営者の軸=経営の基本がないまま、独自の仮説を立て、勢いで施策を実施し続けた結果なのかも知れません。
経営の全体像を理解した上でさらに「経営の勉強」を実践し続けると、
日々新たに発信される、あらゆるビジネス情報も自社のどの分野に活かせそうか?
本当に今必要な情報なのか?など「情報選別」の精度が高まります。必要な情報を元に、経営者として効率的・効果的な経営の仕事を実現できるようになります。
どこかのタイミングで経営者は、この経営の基本をしっかりと固める「経営の勉強」をしておくと、それ以降の経営に大きなアドバンテージを得ることができます。
また、判断に悩み迷うときに経営のガイドラインとして、勉強をした「経営の基本」に立ち戻ることができるというのは、経営者にとって自信を持って経営に取り組める安心材料です。
さらに、事業を幹部社員と共に見直したり議論をするときも、社長の思いつきではなく「経営の基本」を軸に考え話すと理解・納得が得やすくなります。
しかし、この「経営の基本」という経営の勉強をまとめたものがない、学ぶ機会がない、という理由で経営の勉強として実施できていない経営者がほとんどです。
そこで、経営の基本をおさえ、経営の全体像を理解する「経営の勉強」方法として、私たちがオススメしているのが「経営の12分野」というものです。複雑な経営を、シンプルに12の要素と構造にまとめ、経営者個人のレベルや時間に合わせて習得しやすくした「経営の勉強」プログラムです。
「経営の12分野」講座とは > https://president-ac.jp/service/

経営の12分野は、経営を「商品力」「営業力」「管理力」という大きな3つの要素に分けて学ぶ、わかりやすいプログラムです。さらにこれら3つの大分野を、さらに4つずつに分けることで、経営に必要な要素を網羅的に詳しく習得することができます。
「3大分野×4つの要素=経営の12分野」ということで、経営を体系的・総合的に理解して実践できる、経営の勉強プログラムです。
経営に欠かせない要素を漏れなく勉強するので、自分が考えられていなかった経営に必要な事項や弱点もカバーをして強化することができます。
経営の勉強で必要な12個の分野を下記に記載します。
まずは、この12分野を知るところから、経営の勉強をはじめることをおすすめします。
【商品力】
ミッション
商品力
ポジショニング
ブランディング
【営業力】
集客力
見込客フォロー
サイレントセールス
CLVマネジメント
【管理力】
経理・財務
チームビルディング
仕組み化
投資とリスクマネジメント
経営の12分野の詳細は「経営とは何か?」
の無料レポートで説明していすので、こちらも御覧ください。
4 まとめ
本レポートでは、経営の勉強をはじめるときに考えるべきこと、
注意すべきことなど紹介しました。
そもそも、経営を勉強することは経営者にとって、経営を続けるために
なくてはならない活動の一つです。
経営者として経営を行う際に必要となる仮説力を高めることであり。
自社の経営を見直すためのガイドラインであり。迷い悩む時の判断基準となる羅針盤です。変化が激しい現代では経験豊かな経営者でも、
経営を勉強をし続けなければ、直面する新たな状況や課題に対応することができません。
しかし、闇雲に経営の勉強をしても、情報の海に溺れてしまって、時間とエネルギーを無駄にしてしまいます。
だからこそ、経営者はまず経営の基本=「経営の全体像を理解すること」からはじめることが大切です。経営をするために必要な要素はあまりに多岐にわたり、全体像を個人が把握しようと、書籍を読んだりネット情報を見ながら習得することは困難です。
経営の全体像を理解するために、体系的・総合的に、経営の勉強をする
専用プログラムがやはり必要です。そこで、私たちが行きついた答えが
「経営の12分野」という体系的・総合的な経営の勉強プログラムです。
最後に、経営の勉強はなかなか時間を確保しにくいものです。
だからこそ、経営を勉強する時間をあらかじめスケジューリングする
という方法をオススメしています。
予定を先に確保することで、仕事の一部にして周囲にも共有します。
忙しいからこそ、勉強をする時間までに仕事を効率的に終わらせようと
いう工夫も生まれます。
経営を勉強することを決めない限り「経営の勉強をしなければ」と思い
ながらもできない、中途半端な状態がこれからも続きます。
その結果、経営者としての成果も自信も得られないままの、モヤモヤと
した日々が続いてしまうかもしれません。
経営の勉強は社長の仕事の1つです。
経営の勉強の取り組み方を本レポートを参考していただき、経営の成功
に向けて確かな一歩を踏み出していただければ幸いです。
その他のオススメ
無料レポート


|
「経営とは何か?」〜経営の要素と構造〜全ての経営者にとって永遠の課題。私も悩んだ。会社経営で頭から決して離れない社長の宿題。この経営レポートは必読です!
|


|
「社長の仕事とは?」 |


|
「 経営を勉強する重要性 」 |

|
なぜ社長は「経営に失敗する」のか? |

|
数千人の起業家を見てきて分かった |
|
「 経営戦略とは? 」 |
|
経営戦略で迷った時に、考えるべき「3つのこと」 |
|
生き残る会社をつくる「守り」の経営〜守りの重要性とは?〜経営における「守り」の重要性について説明します。未来に生き残る会社をつくるためには欠かせない経営視点です。
|
|
「事業承継 |
|
「社長の仕事」122項目のチェックリスト「社長の仕事」大全がここに完成!社長が明日からやるべき鉄板チェックリストを伝授します!
|
|
「経営セミナー活用の基本」 |
|
「経営計画とは?」 |
|
「経営の勉強」をはじめたくなったら〜まず最初に社長がすべき「経営の勉強」とは?〜社長が経営の勉強をするにあたり、はじめの一歩として読んで欲しい内容をまとめました。
|
|
「仕事の仕組み化〜経営を効率化するために社長が行うべき仕組み化とは?〜」「社長の仕事」に専念するために社長が行うべき「仕事の仕組み化」についてまとめました。
|
|
「チームビルディングとは?〜「チームビルディング」の本当の意味とは?目的や3つの手法を詳しく解説〜」チームビルディングとは何なのか?をまとめました。チームビルディングを実践するためのノウハウを身に着けましょう!
|
|
「会社の目的は「幸せ」になること〜会社の目的は利益ではない〜」「会社の目的」についてまとめました。利益ではなく幸せを目指すべき理由とは?社長が目指すべきゴールをお伝えします。
|
|
「戦わない経営とは?〜全国の経営者の声から実践のヒントを掴む〜」「戦わない経営」とは何なのか?をまとめました。全国の戦わない経営実践者の声から事業成功のヒントを見つけましょう。
|
|
「起業の技術とは?〜書籍を超えた実践ヒントをお届け〜」「起業の技術」とは何なのか?をまとめました。書籍より1歩詳しい解説からヒントを見つけましょう。
|
|
「マイクレドとは?〜ブレない人間になるために〜」「マイクレド」とは何なのか?をまとめました。芯のあるビジネスパーソンになるために必要なマイクレドとは何かをまとめました。
|
|
「だから部下がついてこない〜経営者・リーダーの常識をくつがえす、組織づくりの秘訣とは?〜」経営者が悩む組織づくりについて、その秘訣をまとめました。 経営に必要な組織づくりの重要ポイントをお伝えします。
|
資料が欲しい
の詳しい資料を送付します。




















































